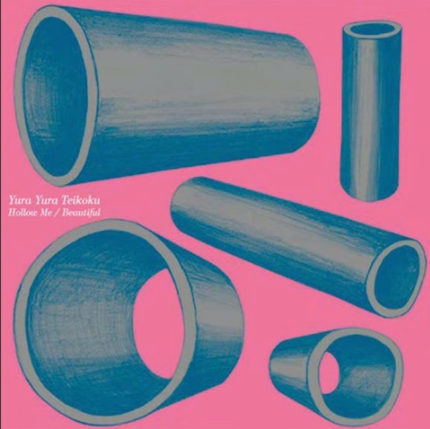星が見える。これは驚くべきことだ。
この奇跡が可能になるために、いったいいくつの宇宙的偶然が必要だったか、
改めて数えてみよう。
星が見えるには、まずもって空が晴れている必要がある。
地球の空は曇ることもあるが、しかし待てば晴れる。
金星のように何万年待っても厚い雲に覆われたままの空とは違う。
金星に知性ある生き物がいたとしても、天文学は発達しなかっただろう。
地球の空が晴れる前に宇宙そのものが晴れている必要があった。
最初期の混沌状態から物質と光が分かれ、その光が伝播できるだけの空間が生じる。
宇宙の晴れ上がりだ。そして星が生まれる。
星の光が何年か、何千年か、何億年かかけて地球に届く。
そしてそこにヒトがいる。
光を感知する器官と、その意味を考えられる脳、
宇宙の全容を想像するための知識を持ったヒトという生物の一個体、
つまりぼく、がそこに立って、星空を見上げている。
…
そういう偶然の連鎖の果てに、
ぼくが星を見てきみたちを思うということが可能になった。
それが偶然なのか必然なのかという議論もあるだろう。
ともかくヒトは星を見ることができるし、
星の世界へきみたちを送り出すこともできた。
「一九七七年に旅立った二人への手紙」より
池澤夏樹をとても好きなのだけど、読んでいない作品のほうが多いかもしれない。
なんか、好きすぎて手を出せない、みたいな。
この2007年発行のlyricalな小品集もノーチェックで、たまたま入った古本屋で見つけて、手に取って、開いた最初のページの「星が見える。これは驚くべきことだ」の1行に降参した。
きみたち、というのは、1977年に打ち上げられて今も旅を続けている2機の探査機ボイジャーのこと。
私たちは、宇宙をゆく無人探査機をなぜ擬人化してしまうんだろうね。
躯体からアンテナやら電池パネルやら突き出した、ただの無骨な金属の塊なのに。
JAXAが飛ばした惑星探査機「はやぶさ」が帰還して大気圏に突入して燃え尽きた時には、鼻の奥がツンっとしたりして。
池澤夏樹は1994年にフリーマン・ダイソンに会った時に、ボイジャーに「愛すると言いたい気持」を抱いていることを告白し、ダイソンから「私も彼らに対して同じように感じている」と返事をもらったそうだ。星の世界へ送り出される、愛おしいモノ。なんだろうね、この感傷は。
ヒトが、ホモ・サピエンス・サピエンスが、宇宙の片隅でひとりぼっちだっていうのを、星を見ることで知ってしまったからなのかな。
「やがてヒトに与えられた時が満ちて・・・」は、種としてのホモ・サピエンス・サピエンスの時間が尽きた後にヒトはどこへ行くのか、どこかに行けるのか、たどり着くと言える場所はあるのか、、、そんな寄る辺ないサミシサが創造させた物語だ。
宇宙に浮かぶ植民都市では、追憶は禁じられている。
地球との繋がりは途絶え、子どもが生まれることは稀で、衣食住足りて希望がない。
追憶さえも禁じられて、ひとは生きていけるのかな。寂しい淋しいさみしいねぇ。
冒頭には6ページほどのショート・ストーリーが四編載っているのだけど、「ボイジャーへ」、「明日宇宙へ行く自分へ」、「いるかどうかもわからないあなたへ」、「終末論研究者が死に際に」語りかけている。
誰かに、自分以外の誰かに、語りかけずにはいられない。それほどに孤独でサビシイんだね。我々、ホモ・サピエンス・サピエンスは。
そりゃぁ、誰かに出会いたい思いを託して、途方もない時間の彼方へ送り出される探査機が愛おしくないはずがないわね。
160ページくらいしかない薄い本なんだけど、これも一気に読み終えたくなくて、一編一編、ゆっくりと何日もかけて、間に他の本もはさんで、読んだ。
周回する役目を終えて地球と別れを告げる
人工衛星のキモチ。愛おしい。
検索して知った惑星探査機ボイジャーの現状。
1号機も2号機も太陽系の外に出て飛び続けている。2024年現在、まだ通信は繋がっているけれども2025年頃には原子力電池が尽きて稼働が停止するらしい。
その後も、慣性の法則で飛び続ける。
ほんとうに、ひとりぼっちになる。話しかける相手もいない。
どこまでいくのかな。
どこかの星の重力に捕まってしまうのかな、墜落して燃え尽きてしまうかもしれないね。
もしかしたらもしかしたら。
百億の偶然が重なった奇跡の果てに、誰かに拾われることもあるのかな。
その誰かは、チャック・ベリーを聞いてイカシテルって思うだろうか。
そんな奇跡が起こったとしても、きっとその頃にはホモ・サピエンス・サピエンスは存在しないし、そんな奇跡を知りようもない。
*
星が見える。
そんな奇跡をいま味わおう。