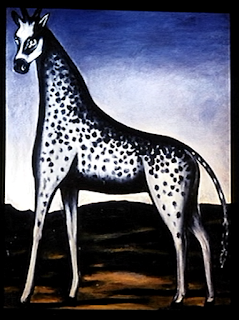きょう、三月三十日午前十時、わたしの知らない間に
レンギョウの最初の花が咲いた。
この歴史的な瞬間を、どんなことがあっても見逃してはならないと思って
小さな黄金の鞘に似た、いちばん大きな芽を
三日前からわたしは見張っていた。
雨が降るかな、と思ってわたしが空を見あげた間に
その瞬間が来た。
あしたはもう、しなやかな若い枝が
どの枝もいちめんに黄金の星をまきちらしたようになるだろう。
ひきとめようとしても、ひきとめることはできない。
カレル・チャペック「園芸家の12ヵ月」
子どもの頃、この家の南側はレンギョウの垣根だった。垣根の先は空き地で陽当たりが良くて眩しいような明るい黄色のその生垣が大好きだった。
そろそろ咲くかな、もう咲くかなと「歴史的瞬間」を見逃すまいとしているのに、花はいつだって知らぬ間に咲く。
どんな花も楽しみだけど、春一番に咲く“黄色”の輝きは格別。
たたんだ扇をひらくがいい。うぶ毛をはやしてねむっている芽よ、目をさませ。
スタートの命令が、もう出たのだ。
楽譜にのらない行進曲の、はなやかなラッパを吹き鳴らすがいい!
陽をうけて光れ、金色の金管楽器。
とどろけ、太鼓。吹け、フリュート。
幾百万のヴァイオリンたちよ、おまえたちのしぶき雨をまきちらすがいい。
茶いろとみどりのしずかな庭が凱旋行進曲をはじめたのだ。
カレル・チャペック「園芸家の12ヵ月」
3月の終わり。みどりが目を覚まして、花芽が動き出すこの季節の歓びが良く伝わる(笑)
笛太鼓を打ち鳴らすパレードのような?大袈裟なようだけど、庭をいじる人は、樹々の、みどりの凱旋に、密かに小躍りしているのです。
ネモフィラ。
スーパーでの買い物のオマケで種がついていて蒔いた。
手前は小鳥につまみ食いされた。
ギボウシ。
明るいライムグリーンに白い斑入りの品種。
昨秋買った。
大きくなったら庭におろそう。
水仙。
庭に置きっぱなしの鉢。
何年も咲かなかったんだけど。
なにか思い出したのかな。
地植えのギボウシ。
父が鉢植えにしていたのが根が回ってしょんぼりしてたので
株分けして庭のあちこちに植えて増えた。
ギボウシの自然な株の姿形が好き。
手前はウツギ、卯の花。
もうツボミがたくさんついている。
ナミアゲハの越冬蛹。
無事に羽化していた。
キンカンを伐っていてみつけた。
2センチちょっと、小さくて真っ黒で。
先々週の気温の高かった時にも羽化してなくて、生きてるのかなぁと思ったけど今日羽化していた、らしい。蝶の姿はみていないけど。
昨秋から、10、11、12、1、2、3月。半年、この姿でここで生き延びたんだね。
花の咲くのを待って羽化するというのを知って驚く。先々週の初夏のような気温にも騙されなかったんだよね。この一週間の雨と気温の高下をちゃんとやり過ごして、いろんな花が咲きだすタイミングで羽化。なんて賢い。
ベランダのアゲハ保育園の子達もどこかで羽化できてるといいな。
そうだ、レモンの種を蒔こう。